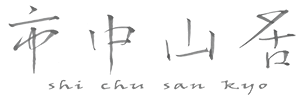市中山居とは

街にいながら 自然と人と 共に暮らす
千利休は、街中に山の風情を感じる庭を設え、茶室を構えました。
ここを訪れる人はまるで、
山中でたどり着いた小屋で、一服のお茶を振舞われ、
疲れと心が癒されるような体験をします。
市中山居とは、
街中にいながら、山の風情を感じ、一期一会を味わうという、
千利休の侘び茶の世界観を具現化したものです。
その世界観は文化となり、住まいにも息づいています。
例えば、「放浪記」などの作者、林芙美子の自邸。
現在も新宿区立林芙美子記念館として遺されています。
(上の写真、通常建物内は入れません)
彼女は、現在の新宿区中井に土地を買い、
建築家 山口文象に設計を依頼して、
昭和十六年に三十坪の平屋を建てました。
それは、質素ながら丹精に作られた草庵のようです。
竹林の中にひっそりと構える玄関をくぐり、
居間に座りながら庭を眺めていると、心が静まります。
当時ここで、彼女が家族や客人と食卓を囲み、
会話を楽しむ姿を想像すると、心が和みます。
私たちは、市中山居を現代にも受け継ぎ、
街にいながら、自然と人と共に暮らす住まいを
設えたいと考えています。
RIMG0107_fortop.jpg)
市中山居の暮らしぶり

自然に生かされる よろこび
茶室では山の風情を感じられるように、市中山居では「自然との暮らし」を大切にしています。私たちが設計した自邸「通庭が楽しい家」で暮らして気付いたのは、
「自然は私たちに向け、日々多様な姿で語りかけ、一年を通して恵みを与えてくれる」ということです。
例えば、日々の移ろい。
朝、鳥の声と朝日で目覚め、アウトドアリビングで新鮮な空気を腹一杯吸い込みます。そして朝食は庭の鳥と一緒にとります。
昼、子供たちの遊ぶ声に元気をもらいながら庭いじりを楽しみます。そして摘んだ草木を器に生け、部屋に飾ります。
夜、ヒバが香るお風呂で疲れを癒します。風呂上り、濡れ縁で心地よく流れる風を楽しみ、夕涼みをします。
例えば、季節の恵み。
春、お隣さんの桜と梅を借景にさせて頂き、家の中でお花見を楽しみます。
初夏、テラスに机と椅子を並べ、ランチをとりながら木漏れ日と風を感じます。
夏、昼間は庭に設えた石積みに打水し、涼を得ます。夜はアウトドアリビングから近所の花火大会を見ます。尺玉の迫力ある音を聞きながら、枝豆とビールを味わいます。
秋、濡れ縁にススキを飾り、鈴虫の音を聞きながら、静かに月見をします。
冬、薪ストーブを焚きます。パチパチと鳴らし、ほのかに甘い香りを放ちながら揺れる炎を眺めます。ゆったりと流れる時間の中で、心と体が芯まで温まります。
そんな日々の暮らしで、自然と人は分かち難くつながっており、人は自然に生かされているという実感が湧いてきます。

人に生かされる ありがたみ
市中山居では、一期一会、「人との出会い」を大切にしています。私たちが自邸で暮らして気付いたのは、
「自然だけでなく、人との結びつきがあれば、暮らしはより安心で豊かになる」ということです。
例えば「向こう三軒両隣」のようなご近所付合い。
子育て、介護、防災など困った時に助け合えるだけでなく、イベントでは楽しみを膨らましてくれます。
そこで私たちは、人とのつながりのある設えを大切にします。
人が集まれる居間を設けるのはもちろん、ご近所さんとの井戸端会議として、駐車場や玄関前にベンチを設えたり、道路際に草木を植え、ご近所さんにも緑の潤いをお裾分けしたりします。
また、つながりだけでなく「適度な距離感」を保つことも大切にします。
周囲に対して住まいを閉ざすことなく、緩やかに仕切れるよう、低めの塀を設けたり、自分達の住まいの窓は、お隣さんの窓と正面で見合わないよう、位置や大きさに心を配ったり、お隣さんとの家の間に緑を設けたりします。
我が家ではご近所さんと、薪ストーブを楽しみながら牡蠣を味わう冬のイベントを毎年行っています。薪ストーブで出た灰は肥料として、ご近所さんにお裾分けもしています。
一日の終わり、人に支えられて生かされていることに感謝します。そうすると、明日に向けて頑張る気持ちが湧いてきます。
市中山居の暮らしづくりをお手伝い
_20151121c.jpg)
私たちが考える市中山居とは、
街の中にいながら、自然と人と共に、生きる喜びを感じ、人生を謳歌して暮らす住まいです。
そんな暮らしづくりを私たちと一緒に実現しませんか。
私たちが大切にしている「こだわり」と「下ごしらえ」で、あなたの暮らしづくりをお手伝いします。